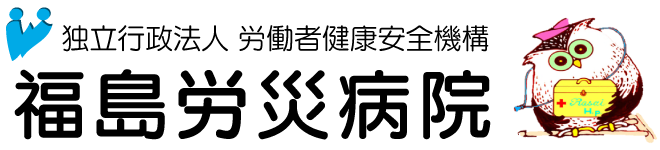循環器科
概要
対象疾患
- 虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞など)
- うっ血性心不全
- 不整脈
- 心臓弁膜疾患
- 心筋疾患
- 高血圧症
- 先天性心疾患
- 大動脈疾患
- 末梢血管疾患など
特色
当科はいわき市のみならず浜通り地区の循環器疾患の患者に対し外来診療、入院診療、救急診療、産業保健を通して近隣の医療機関と連携を密にして対応しております。
地域の医師減少傾向の中で常勤医5人体制が維持できておりますので、これからも常時24時間緊急オンコール体制で急性心筋梗塞などの救急医療に積極的な対応を行って参ります。
80列CTによる冠動脈の評価、心臓超音波検査、負荷・24時間ホルター心電図、心臓核医学、心臓カテーテル検査治療(橈骨動脈穿刺)などにより今後も患者さんの低侵襲検査・治療に努めて参ります。今後も地域の診療所・病院との連携を強化し地域医療の更なる充実に努力する所存です。
高齢化の進むいわき市で当院は地域支援病院として合併症(認知症、呼吸器疾患、腎疾患、運動器障害など)を伴った高齢の循環器疾患患者さんの診療依頼が増えつつあり、その対応は益々重要となっております。患者さんを中心に看護師、薬剤師、臨床検査技師、放射線科技師、栄養士、理学療法士、作業療法士、心理判定員、MSW(medical social worker)、医療事務職員とともにチーム医療の重要性を推進しております。電子カルテが導入され業務の効率が飛躍的に向上し大きな力になっております。
循環器診療には心臓血管外科との連携が欠かせませんが幸い近隣のいわき市立医療センターと病病連携して対応しております。また業務・勤務形態の複雑化や経済事情の変化による勤労者の方々のストレスの増大、健康障害に対して産業医活動、健康相談を通して対応しております。
当科は循環器疾患を診療しておりますが初診・再診の患者さんにおいて院内他科と連携し幅広い対応に努めております。
他の医療機関との連携
要精査の患者さん、急性期(重症、不安定)の患者さんを受け入れ当科で治療し、病状が軽快、安定後に地域のかかりつけの先生方に退院後の外来経過観察加療を依頼しております。その際には緊密な他の医療機関との連携が必要となります。
当科では症状変化の際に常時24時間オンコール体制で対応しております。 いわき市病院協議会救急委員会に参加し救急隊員との検討会、市民フォーラムの企画などに積極的に参加しています。
かかりつけの先生方と連携し冠動脈形成術後、ステント留置術後の薬物治療、特に最狭窄の著明な減少をもたらした薬剤溶出ステントによる遅発性ステント血栓症の予防のため抗血小板薬の外来管理をお願いし更に半年後に心臓カテーテル検査にてステント留置部の冠動脈を評価しております。かかりつけの先生方では困難なペースメーカー管理なども当科(ペースメーカー専門外来)で管理しております。特に糖尿病を有する患者さんについては心動脈硬化の進行による血管疾患発症のリスクが高いため市内の糖尿病専門医と連携し1泊2日の教育入院で対応しております。
現在、心筋梗塞の急性期を乗り切った患者さんが慢性心不全を発症する数が増えていると報告されており慢性心不全の予防がますます重要になっております。種々の薬剤が大規模調査から心不全に対する有効性が確認されています。かかりつけ医の先生方と連携を密にして慢性心不全の発症が危惧される患者さんを対象に非侵襲検査としての心エコー、心臓核医学、造影CTを活用し病態把握に努め診療のための情報をお伝えしております。更に心不全に対する非薬物療法としてCRT(心臓再同期療法)の適応患者さんについては福島県立医科大学循環器・血液内科学講座と連携し対応致します。心電図健診にて要精密検査と判定された方々についての二次健診に今後も積極的に取り組んで参ります。
認定・研究内容
施設認定資格
- 日本循環器学会指定循環器研修施設
- 日本内科学会関連施設
個人認定資格
- 日本内科学会総合内科専門医
- 日本内科学会認定医
- 日本内科学会指導医
- 日本循環器学会専門医
- 日本核医学会専門医
- 日本核医学会PET認定医
- 労働衛生コンサルタント(保健衛生)
- 日本職業災害医学会(労災協力医)
- 日本医師会認定産業医
- 日本心臓リハビリテーション学会
ガイドラインに基づいた診断治療に努め各自、最先端の循環器疾患の診断、治療の習得に日々研鑽を積んでおります。毎週シネカンファランス、症例検討会を開催し討論を行い診断治療に効果を上げています。初期・後期研修を希望される先生方については当科の研修を通して救急を含め循環器疾患患者さんの幅広い対応が可能となり急性期~慢性期の病態を把握する臨床力を身に付けられるものと確信致します。
医師紹介
副院長/小松 宣夫
| 医師よりみなさまへ 心筋梗塞や心不全などの心臓病のほか足の動脈が詰まる閉塞性動脈硬化症など、循環器疾患全般の診療に携わっております。毎週月曜日と、火曜日は午後の外来を担当しています。よろしくお願いいたします。 |
|
【略歴】
【所属学会】
|
【専門資格】
【専門分野】
|
主任部長/吉成 和之
| 医師よりみなさまへ こんにちは。循環器科の吉成です。植田町出身で平成13年より労災病院に勤務しております。現在、広く心臓病を診ていますが、病気というものはやはり早期発見・早期治療が大事ですので”胸が痛い””動悸がする””息切れがある”等、心臓と思われる症状があれば、早目に外来を受診することをお勧めします。 |
|
【略歴】
【所属学会】
|
【専門資格】
【専門分野】
|
部長/渡邉 康之
| 医師よりみなさまへ 平成15年4月より当院循環器科へお世話になり勤務させていただいております。出身は郡山で、それまでいわきの医療機関に勤務したことはありませんでしたので、着任後そのカバーしなければならない医療圏の広さにびっくりしました。 これからも出来る限り浜通り地区の循環器医療に貢献したいと思っております。 宜しくお願いいたします。 |
|
【略歴】
【所属学会】
|
【専門資格】
【専門分野】
|
部長/三戸 征仁
| 医師よりみなさまへ 循環器科の三戸征仁と申します。出身地は地元いわき市です。平成18年より当院で循環器疾患の診療をさせて頂いております。特に虚血性心疾患及びその原因となる生活習慣病の早期発見・治療に力を入れており、外来で冠動脈CTを用いたスクリーニングも積極的に施行しておりますのでお気軽にご相談下さい。 今後も地元いわき市の循環器診療のお役に立てるよう頑張りたいと思っておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 |
|
【略歴】
【所属学会】
|
【専門資格】
【専門分野】
|
部長/渡邊 俊介
【略歴】
【所属学会】
|
【専門資格】
【専門分野】
|
部長/鈴木 重文
| 医師よりみなさまへ 運動不足などの生活習慣の変化、カロリー過多、生活環境の欧米化、24時間型の現代社会、経済事情の変化によるストレスの増大、業務・勤務形態の複雑化、高齢化などにより動脈硬化の進行による心血管疾患が増加しております。当科では循環器科医師と医療チーム全員が力を合わせて診断、治療の研鑽向上に努めております。現在、24時間常時オンコール体制で救急医療に積極的に対応しております。今後も様々な検査、薬剤、情報提供、手術などを通してひとりひとりの患者様の健康の回復と維持増進に貢献できるよう地域のかかりつけの先生方と協力して努めて参ります。 |
|
【略歴】
【所属学会】
|
【専門資格】
【専門分野】
|
実績
│2023年│2022年│2021年│2020年│2019年│
2023年
入院患者様内訳
| 病 名 | 症例数 | 病 名 | 症例数 |
|---|---|---|---|
| 心筋梗塞 急性 | 29 | 呼吸器疾患 | 17 |
| 心筋梗塞 陳旧性 | 20 | 腎・尿管疾患 | 15 |
| 狭心症 | 109 | ペースメーカー電池交換 | 14 |
| 血栓性静脈炎 | 7 | 熱中症 | 6 |
| 心不全 | 185 | 肺炎 | 23 |
| 肺塞栓症 | 5 | 貧血 | 6 |
| 心筋症 | 4 | 新型コロナ感染症 | 23 |
| 不整脈 | 33 | インフルエンザ感染症 | 3 |
| アテローム硬化症 | 4 | 廃用症候群 | 4 |
| 大動脈瘤解離 | 2 | 老衰 | 3 | 動脈塞栓 | 2 | 嚥下障害 | 3 | 慢性虚血性心疾患 | 2 | 脱水症 | 3 | 蜂巣炎 | 3 | ショック | 2 | めまい症 | 7 | その他 | 34 | 脳血管障害 | 2 |
| 計 | 576 | ||
各種検査・治療
| 症例数 | |
|---|---|
| PCI治療(穿刺部位:橈骨動脈59・大腿動脈46) | 105 |
| PTCR(経皮的冠動脈内血栓溶解療法) | 0 |
| POBA(経皮的冠動脈形成術) | 23 |
| STENT(経皮的冠動脈ステント留置術) | 81 |
| 心臓カテーテル検査(Cine angio)(穿刺部位:橈骨動脈137・大腿動脈63) | 200 |
| EPS(電気生理学的検査)、アブレーション | 0 |
| IVUS(血管内超音波検査) | 86 |
| アセチルコリン負荷 (冠攣縮性狭心症の薬物誘発試験) |
5 |
| 心筋生検 | 16 |
| PPI(経皮的動脈形成術) | 2 |
| IABP(大動脈バルーンパンピング法) | 3 |
| ペースメーカー植込・交換術 | 20・12 |
| IVC filter ( 下大静脈フィルター留置術) | 0 |
| 冠動脈CT | 93 | 心臓MRI | 23 |
生理検査
| 症例数 | |
|---|---|
| 心臓超音波検査 | 2693 |
| ホルター心電図 | 421 |
| ABI | 82 |
| 脈管エコー | 379 |
| 運動負荷心電図 | 35 |
心臓核医学検査
| 症例数 | |
|---|---|
| Tc安静心筋血流シンチ | 20 |
| Tc薬物負荷心筋血流シンチ | 8 |
| MIBG心臓交感神経シンチ | 0 |
| BMIPP心筋脂肪酸代謝シンチ | 1 |
| 肺血流シンチ | 3 |
2022年
入院患者様内訳
| 病 名 | 症例数 | 病 名 | 症例数 |
|---|---|---|---|
| 心筋梗塞 急性 | 22 | 糖尿病 | 4 |
| 心筋梗塞 陳旧性 | 21 | 大動脈解離 | 2 |
| 狭心症 | 76 | 脱水症 | 4 |
| 心臓弁膜症 | 5 | 血栓性静脈炎 | 2 |
| 心不全 | 208 | 脳血管障害 | 4 |
| 高血圧症 | 3 | 呼吸器疾患 | 30 |
| 肺塞栓症 | 5 | 腎不全 | 15 |
| 不整脈 | 42 | ペースメーカー電池交換 | 23 |
| 心筋症 | 1 | 新型コロナウイルス感染症 | 3 |
| 心膜炎 | 4 | その他 | 52 |
| 計 | 526 | ||
各種検査・治療
| 症例数 | |
|---|---|
| PCI治療(穿刺部位:橈骨動脈36・大腿動脈61) | 69 |
| PTCR(経皮的冠動脈内血栓溶解療法) | 0 |
| POBA(経皮的冠動脈形成術) | 8 |
| STENT(経皮的冠動脈ステント留置術) | 60 |
| 心臓カテーテル検査(Cine angio)(穿刺部位:橈骨動脈97・大腿動脈62) | 159 |
| EPS(電気生理学的検査)、アブレーション | 0 |
| IVUS(血管内超音波検査) | 64 |
| アセチルコリン負荷 (冠攣縮性狭心症の薬物誘発試験) |
4 |
| 心筋生検 | 9 |
| PPI(経皮的動脈形成術) | 0 |
| IABP(大動脈バルーンパンピング法) | 5 |
| ペースメーカー植込・交換術 | 31/36 |
| IVC filter ( 下大静脈フィルター留置術) | 0 |
| 冠動脈CT | 91 |
生理検査
| 症例数 | |
|---|---|
| 心臓超音波検査 | 2852 |
| ホルター心電図 | 445 |
| ABI | 77 |
| 脈管エコー | 305 |
| 運動負荷心電図 | 35 |
心臓核医学検査
| 症例数 | |
|---|---|
| Tc安静心筋血流シンチ | 18 |
| Tc薬物負荷心筋血流シンチ | 8 |
| MIBG心臓交感神経シンチ | 0 |
| BMIPP心筋脂肪酸代謝シンチ | 2 |
| 肺血流シンチ | 3 |
2021年
入院患者様内訳
| 病 名 | 症例数 | 病 名 | 症例数 |
|---|---|---|---|
| 心筋梗塞 急性 | 36 | 頻拍症 | 4 |
| 心筋梗塞 陳旧性 | 23 | 大動脈瘤(真性、解離性) | 4 |
| 狭心症 | 63 | 肺炎 | 15 |
| 冠攣縮性狭心症 | 4 | 低ナトリウム血症 | 3 |
| 心臓弁膜症 | 5 | ペースメーカー電池消耗 | 21 |
| 心不全 | 181 | その他の心疾患 | 8 |
| 房室ブロック | 15 | 脳梗塞 | 2 |
| 動脈硬化症 | 5 | 呼吸器疾患 | 10 |
| 洞不全症候群 | 8 | 尿路感染症 | 7 |
| 心房細動 | 8 | 腎・尿管疾患 | 11 |
| 虚血性心疾患 | 6 | その他 | 42 |
| 心筋症 | 2 | ||
| 計 | 483 | ||
| 症 例 | 件 数 |
|---|---|
| PCI治療(穿刺部位:橈骨動脈/大腿動脈) | 84(29/55) |
| PTCR(経皮的冠動脈内血栓溶解療法) | 0 |
| POBA(経皮的冠動脈形成術) | 32 |
| STENT(経皮的冠動脈ステント留置術) | 52 |
| 心臓カテーテル検査(Cine angio)(穿刺部位:橈骨動脈/大腿動脈) | 169(84/85) |
| EPS(電気生理学的検査)、アブレーション | 0 |
| IVUS(血管内超音波検査) | 57 |
| アセチルコリン負荷 (冠攣縮性狭心症の薬物誘発試験) |
2 |
| 心筋生検 | 4 |
| PPI(経皮的動脈形成術) | 3 |
| IABP(大動脈バルーンパンピング法) | 1 |
| ペースメーカー植込・交換術 | 29/18 |
| IVC filter ( 下大静脈フィルター留置術) | 0 |
| 冠動脈CT | 91 |
生理検査
| 心臓超音波検査 | 2717 |
|---|---|
| ホルター心電図 | 444 |
| ABI | 99 |
| 脈管エコー(下肢/頸動脈) | 249(132/117) |
| 運動負荷心電図 | 59 |
心臓核医学検査
| Tc安静心筋血流シンチ | 18 |
|---|---|
| Tc薬物負荷心筋血流シンチ | 19 |
| MIBG心臓交感神経シンチ | 1 |
| BMIPP心筋脂肪酸代謝シンチ | 2 |
| 肺血流シンチ | 3 |
2020年
入院患者様内訳
| 病 名 | 症例数 | 病 名 | 症例数 |
|---|---|---|---|
| 心筋梗塞 急性 | 40 | 心筋症 | 5 |
| 心筋梗塞 陳旧性 | 25 | 閉塞性動脈硬化症 | 4 |
| 狭心症 | 75 | 大動脈瘤(真性、解離性) | 3 |
| 冠攣縮性狭心症 | 5 | 脱水症 | 6 |
| 心臓弁膜症 | 2 | 心膜炎 | 2 |
| 心不全 | 166 | 脳血管障害 | 34 |
| 高血圧症 | 5 | 呼吸器疾患 | 35 |
| 肺塞栓症 | 1 | 血栓性静脈炎 | 1 |
| 不整脈 | 36 | 糖尿病 | 3 |
| 腎不全 | 2 | ペースメーカー電池交換 | 18 |
| その他 | 60 | ||
| 計 | 526 | ||
| 症 例 | 件 数 |
|---|---|
| PCI治療 | 102 |
| 穿刺部位 | 橈骨動脈37・大腿動脈65 |
| PTCR(経皮的冠動脈内血栓溶解療法) | 0 |
| POBA(経皮的冠動脈形成術) | 31 |
| STENT(経皮的冠動脈ステント留置術) | 71 |
| 心臓カテーテル検査(Cine angio) | 189 |
| 穿刺部位 | 橈骨動脈92・大腿動脈97 |
| EPS(電気生理学的検査)、アブレーション | 0 |
| IVUS(血管内超音波検査) | 78 |
| アセチルコリン負荷 (冠攣縮性狭心症の薬物誘発試験) |
1 |
| 心筋生検 | 2 |
| PPI(経皮的動脈形成術) | 4 |
| IABP(大動脈バルーンパンピング法) | 2 |
| ペースメーカー植込・交換術 | 18/18 |
| IVC filter ( 下大静脈フィルター留置術) | 0 |
| 冠動脈CT | 129 |
生理検査
| 心臓超音波検査 | 2799 |
|---|---|
| ホルター心電図 | 465 |
| ABI | 126 |
| 脈管エコー | 161 |
| 運動負荷心電図 | 89 |
心臓核医学検査
| Tc安静心筋血流シンチ | 17 |
|---|---|
| Tc薬物負荷心筋血流シンチ | 20 |
| MIBG心臓交感神経シンチ | 0 |
| BMIPP心筋脂肪酸代謝シンチ | 1 |
| 肺血流シンチ | 3 |
2019年
入院患者様内訳
| 病 名 | 症例数 | 病 名 | 症例数 |
|---|---|---|---|
| 心筋梗塞 急性 | 30 | 心筋症 | 5 |
| 心筋梗塞 陳旧性 | 31 | 閉塞性動脈硬化症 | 1 |
| 狭心症 | 109 | 大動脈瘤(真性、解離性) | 2 |
| 冠攣縮性狭心症 | 3 | 脱水症 | 3 |
| 心臓弁膜症 | 10 | 心膜炎 | 0 |
| 心不全 | 187 | 脳血管障害 | 26 |
| 高血圧症 | 39 | 呼吸器疾患 | 35 |
| 肺塞栓症 | 0 | 血栓性静脈炎 | 0 |
| 不整脈 | 2 | ペースメーカー電池交換 | 5 |
| 胸膜炎 | 0 | 糖尿病 | 12 |
| 腎不全 | 4 | その他 | 184 |
| 計 | 688 | ||
| 症 例 | 件 数 |
|---|---|
| PCI治療 | 114 |
| 穿刺部位 | 橈骨動脈42・大腿動脈72 |
| PTCR(経皮的冠動脈内血栓溶解療法) | 0 |
| POBA(経皮的冠動脈形成術) | 18 |
| STENT(経皮的冠動脈ステント留置術) | 93 |
| 心臓カテーテル検査(Cine angio) | 244 |
| 穿刺部位 | 橈骨動脈148・大腿動脈96 |
| EPS(電気生理学的検査)、アブレーション | 0 |
| IVUS(血管内超音波検査) | 99 |
| アセチルコリン負荷 (冠攣縮性狭心症の薬物誘発試験) |
5 |
| 心筋生検 | 4 |
| PPI(経皮的動脈形成術) | 13 |
| IABP(大動脈バルーンパンピング法) | 1 |
| ペースメーカー植込・交換術 | 25/14 |
| IVC filter (下大静脈フィルター留置術) | 0 |
| 冠動脈CT | 125 |
生理検査
| 心臓超音波検査 | 3061 |
|---|---|
| ホルター心電図 | 639 |
| ABI | 190 |
| 脈管エコー | 128 |
| 運動負荷心電図 | 104 |
心臓核医学検査
| Tc安静心筋血流シンチ | 5 |
|---|---|
| Tc薬物負荷心筋血流シンチ | 13 |
| MIBG心臓交感神経シンチ | 0 |
| BMIPP心筋脂肪酸代謝シンチ | 1 |
| 肺血流シンチ | 2 |
診療ガイドライン
冠動脈疾患
- 2020年 JCSガイドライン フォーカスアップデート版 冠動脈疾患患者における抗血栓療法
- 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版)
- 慢性冠動脈疾患診断ガイドライン(2018年改訂版)
- 安定冠動脈疾患の血行再建ガイドライン(2018年改訂版)
(日本循環器学会/日本心臓血管外科学会合同ガイドライン) - 冠攣縮性狭心症の診断と治に関するガイドライン(2013年改訂版)
- 虚血性心疾患の一次予防ガイドライン(2012年改訂版)
不整脈
- 2021年 JCS/JHRS ガイドライン フォーカスアップデート版 不整脈非薬物治療
(日本循環器学会/日本不整脈心電学会合同ガイドライン) - 2020年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン
(日本循環器学会/日本不整脈心電学会合同ガイドライン) - 不整脈非薬物治療ガイドライン(2018年改訂版)
(日本循環器学会/日本不整脈心電学会合同ガイドライン) - 遺伝性不整脈の診療に関するガイドライン(2017年改訂版)
- ペースメーカ、ICD、CRTを受けた患者の社会復帰・就学・就労に関するガイドライン(2013年改訂版)
- 失神の診断・治療ガイドライン(2012年改訂版)
- 臨床心臓電気生理検査に関するガイドライン(2011年改訂版)
- 心臓突然死の予知と予防法のガイドライン(2010年改訂版)
心不全・心筋疾患
- 2021年改訂版 循環器疾患における緩和ケアに関する提言(日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン)
- 2021年改訂版 重症心不全に対する植込型補助人工心臓治療ガイドライン
(日本循環器学会/日本心臓血管外科学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会合同ガイドライン) - 2021年 JCS/JHFS ガイドライン フォーカスアップデート版 急性・慢性心不全診療
(日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン) - 2020年版 心アミロイドーシス診療ガイドライン
- 心筋症診療ガイドライン(2018年改訂版)(日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン)
- 急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)
(日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン) - 心臓サルコイドーシスの診療ガイドライン
- 急性および慢性心筋炎の診断・治療に関するガイドライン(2009年改訂版)
先天性心疾患
- 2021年改訂版 先天性心疾患、心臓大血管の構造的疾患(structural heart disease)に対するカテーテル治療のガイドライン
(日本循環器学会/ 日本心臓病学会/日本心臓血管外科学会/日本血管外科学会/日本胸部外科学会合同ガイドライン) - 2020年改訂版 川崎病心臓血管後遺症の診断と治療に関するガイドライン
(日本循環器学会/日本心臓血管外科学会合同ガイドライン) - 先天性心疾患並びに小児期心疾患の診断検査と薬物療法ガイドライン(2018年改訂版)
- 成人先天性心疾患診療ガイドライン(2017年改訂版)
- 先天性心疾患術後遠隔期の管理・侵襲的治療に関するガイドライン(2012年改訂版)
血管疾患
- 2020年改訂版 大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン
(日本循環器学会/日本心臓血管外科学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会合同ガイドライン) - 血管炎症候群の診療ガイドライン(2017年改訂版)
- 末梢閉塞性動脈疾患の治療ガイドライン(2015年改訂版)
弁膜疾患
- 2020年改訂版 弁膜症治療のガイドライン
(日本循環器学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会合同ガイドライン) - 感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン(2017年改訂版)
肺循環
- 肺高血圧症治療ガイドライン(2017年改訂版)
- 肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン(2017年改訂版)
- 慢性肺動脈血栓塞栓症に対するballoon pulmonary angioplastyの適応と実施法に関するステートメント
診断
- 2021年改訂版 循環器超音波検査の適応と判読ガイドライン
- 血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン
- 心臓血管疾患における遺伝学的検査と遺伝カウンセリングに関するガイドライン(2011年改訂版)
予防
- 2021年改訂版 循環器診療における放射線被ばくに関するガイドライン
- 2021年改訂版 心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン
(日本循環器学会/日本心臓リハビリテーション学会合同ガイドライン) - 心疾患患者の妊娠・出産の適応、管理に関するガイドライン(2018年改訂版)
(日本循環器学会/日本産科・婦人科学会合同ガイドライン) - 学校心臓検診のガイドライン
- 循環器薬の薬物血中濃度モニタリングに関するガイドライン
- 非心臓手術における合併心疾患の評価と管理に関するガイドライン(2014年改訂版)
- 脳血管障害、慢性腎臓病、末梢血管障害を合併した心疾患の管理に関するガイドライン(2014年改訂版)
- 災害時循環器疾患の予防・管理に関するガイドライン
- 禁煙ガイドライン(2010年改訂版)
- 循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン
- 循環器領域における性差医療に関するガイドライン
- 心疾患患者の学校、職域、スポーツにおける運動許容条件に関するガイドライン(2008年改訂版)
共通
- 24時間血圧計の使用(ABPM)基準に関するガイドライン(2010年改訂版)